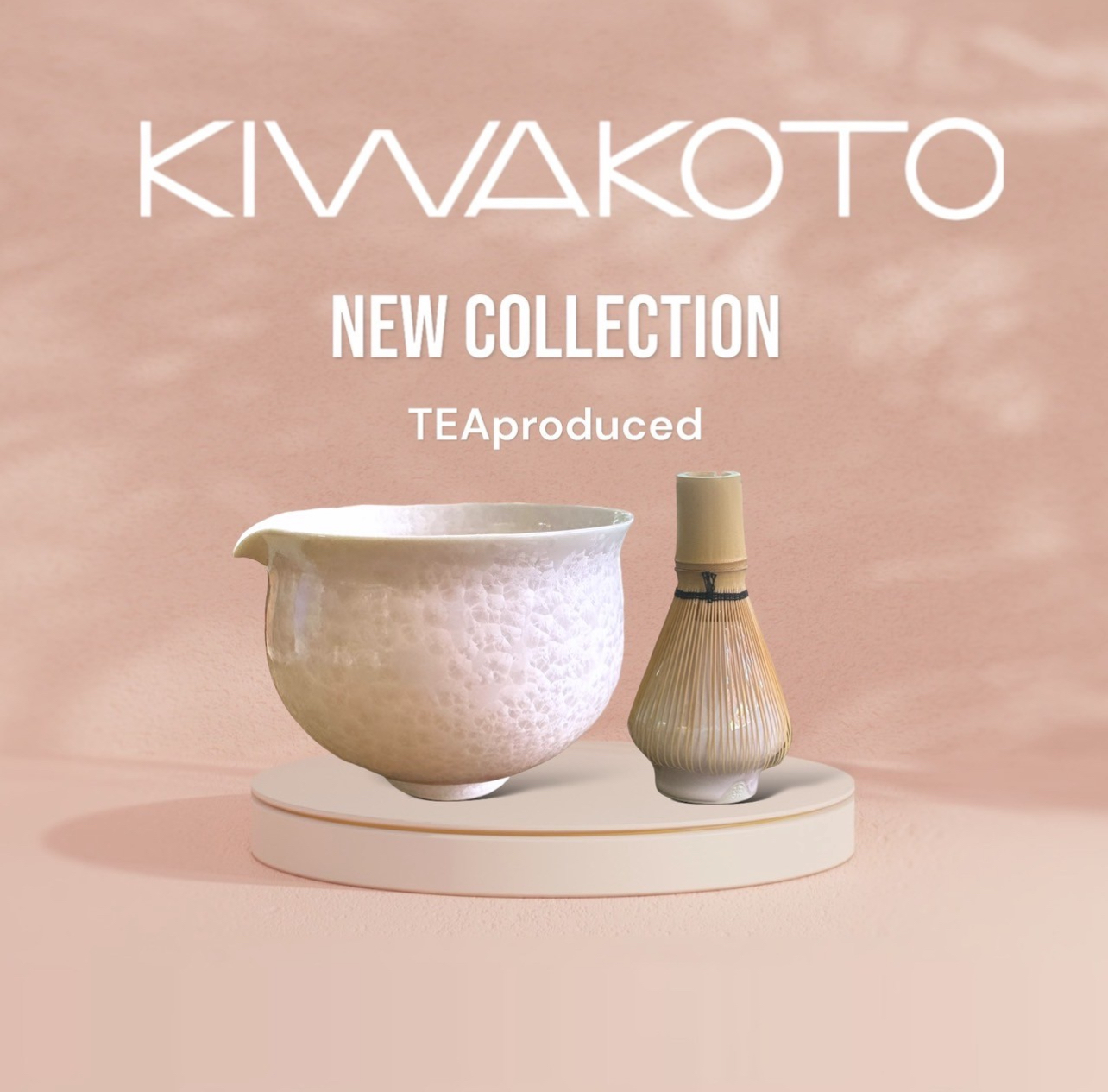「きわこと」とは、現代語でも、とことんまで突き詰めることを「極める」と言い、究極のあり方を「極み」と言う。平安の貴族たちも、栄華を極め、贅の極みを楽しんだ。だが彼らには、その「極み」を「異」にした、つまり極上をさらに突き抜けた世界が見えていた。それを指すのが「きわこと」である。極みを超えた上質さ。比べもののない別格であることを、彼らはこう呼んで褒め、また憧れたのである。
「きわこと」は『源氏物語』にも登場する。主人公光源氏が政界の頂点に立ち、娘を天皇家に嫁がせるという、この物語で最も幸福感に満ちた場面でのことだ。光源氏は娘に持たせる道具を整えるが、その中には冊子本など仮名書きの書物があった。もちろんすべて手書きである。印刷技術は平安時代にもあったが、現在の絵画と同様で、一点ものにこそ価値があったのだ。その時、彼が思い出すのが、かつて六条御息所が何気なく書いた文字の見事さである。「あれは『きわこと』、別格だった」と彼は言う。
六条御息所は、光源氏の女君の一人として知られるが、もとは皇太子妃である。彼女は極上の生活を送る都でも有数の貴婦人であった。だがそれだけではなく、自らが別格の書をものする、教養人であった。それを光源氏に懐かしく思い出させるところに、『源氏物語』の美意識がある。
「きわこと」と共に日常を送る人は、「きわこと」に触れることによって、やがて自らが品格を得、「きわこと」を生み出していく。つまり「きわこと」とは生き方であり、継承されるものでもあるのである。
京都は平安の昔から、こうした価値観を受け継いできた。そして今も、「きわこと」はこの町に息づいている。
ならば今、身のまわりに「きわこと」を置き、それと共に日常を送りたい。極みを超える精神性を、いつもさりげなく感じていたい。光源氏がそうしたように。